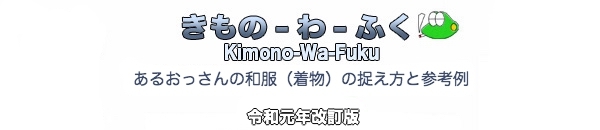バカガエルの寝言戯言:
オレの勝手な推測や意見ばっかなので、テキトーにさらっと読み流しておくれ。なお、特に注釈がない場合の服装は和服ってことで。あと、古い文章は適 時消します。
12月9日:勝手に伝統にすんなよ
和服(着物)でお洒落を楽しもう、ってのは、やりたい人はやればいいし適当でいい人は適当でいいし、服だから各自ご自由にしていただければいいかと。
ただし、例えば季節ごとのコーデを楽しむのが和服文化の「伝統」とまで言うのは、それはいくらなんでも違うんじゃねえかなと思う。
単純な話で、お洒落だのコーデだのを楽しもうと思えば、それだけ和服の「数」が必要になる。例えばメインの長着を春夏秋冬で変えるだけで最低4着、それに合わせて羽織だの帯だのを変えるならそれもまた数が必要になるでしょ。
となると、そんなにたくさんの和服、大昔の人はみんな持ってたのか?って疑問が出てくる。
オレは専門家じゃないから詳しくはわからないけど、子供の頃に習った歴史の授業から考えると、たくさん和服を持ってたのは一部の高収入の人らだけな んじゃないかなあと。お武家さんでもそれなりの役職についてる人とか、町人でもそれなりに商売繁盛させてる店の主人とか、あるいは歌舞伎役者のように今で いう芸能人とかね。
それに「江戸」時代というだけあって中心地だった江戸(東京)の話はよく出てくるけど、実際は各地にも藩(県)があったわけで、現代のような技術やインフラもないんだから、江戸がこうだったから各地も似たようなものとは限らないはず。おまけに江戸時代以前もあるんだしね。
明治時代以降になると、収入やインフラなどは良くなってくるけど、今度は洋服が登場するわけでさ。
まとめると、和服のお洒落を楽しむ文化ってのはもちろんあったと思う。でもそういうのをやれた人らは収入面で限られてるし、それに興味あるなしも考えれば、やってたのは一部の人らだけであって「伝統」とまで言うのは言い過ぎなんじゃないかなと。
要は「着道楽」ですよ。着道楽をするのももちろん着る人の自由だけど、それが和服の伝統だとまで言うのは違うと思うぜ?
まあ一つだけ邪推するなら、着道楽を煽ったほうが売れるんじゃねえの?某ラーメン漫画じゃないけど「情報を食ってる」人って意外といるからさ(笑)
11月21日:普通でいいんだけどなあ
オレの和服(着物)の認識ってのは「単なる衣服、着るもの」なわけで、言うなれば和服が当たり前だった大昔の日本人の認識に近い。
いっぽう現代の和服の認識は、例えば正月や成人式卒業式にお祭りや神仏事、例えば和服のイベントやたまのお洒落や趣味として、言うなれば「特定の日の衣装、装束」という傾向が強い。
どんな認識であっても、和服を着てくれるという点においてはオレは素直に嬉しいよ。これだけ立派な服飾?文化、廃れさせるのはもったいないと思うからね。
ただまあ……正直言うなら、後者のような認識で着てる人が意外といる?ってのは、ちょっとさびしいというか興ざめするというか。「現代」なんだから仕方がないんだろうけど。
もっと普通に、洋服と同じような感覚で着られないもんかなあ……。
11月5日:ある意味条件が揃ってた
30歳代のときに私服の洋服をほとんど捨てちゃったけど、オレはおそらく捨てやすかったんだと思う。
もともとファッションやお洒落どうこうにはほとんど興味なくて、地味な服装でもいいから裸じゃなきゃいいやぐらいだったので、お高い洋服は持ってないしそもそも滅多に買うことがなかった。なので、捨てるのも簡単だったというか量が少なかったというか。
で、服装に無頓着?なオレに和服はぴったりだったわけよ。
作務衣は上下が対になってるし長着も上下一体型だし、そのまま着るだけでシャツとズボンの組み合わせを考えなくて済むでしょ。おまけに「和服」なので洋服の流行とか関係ないし、着慣れてなくても適当に着てるだけでぱっと見は「それなり」だしね。
プラス、いわゆるインドア派なので、例えばスポーツなど洋服(スポーツウエア)が必要な趣味もなかったし、例えば町内活動など機動性が必要なら作務衣、なんなら作業服でもいけるわけで。
となると……もう私服で洋服を着る理由というか必要がなくなったし、洋服より和服のほうが着たいし、だったら思い切って捨てちまおうかってなったわけ。
ただしそうなると、家の内でも外でも(作業服を除けば)当然ながら和服しか着られなくなるので、ちょっとキツイなあって思うかもしれない。
でも、和服を着るようになっていきなり洋服を全部捨てたわけじゃない。和服と洋服の両方を着ながら少しずつ和服の比重を増やしていって、慣れることも含めて10年近く?下準備というか移行期間があったから、そんなに変化はなかったよ。
ついでに言えば、ふんどしオンリーになったのも和服を着る頻度が上がったオマケみたいなもんだよ。和服がただの衣服であるように、ふんどしはただの下着だしね(笑)
10月29日:加筆修正
なにげにサイトのほうを眺めてたら、袴のときのウ〇コをどうするか書いてなかったのに気づいたので「トイレのやり方」を加筆修正しました。
で、その作業やっててふと思ったんだけど、女性の帯の位置が男性に比べて高いのって、トイレの関係もあるのかなあと。女性の帯というか着方って、男性より相当手間がかかる?ので、帯を解かなくても用が足せるようになってんのかなあと。
それに加え、大昔は和式しかなかったんだから余計にかなあと。まあ実際のところはわからんけどね。
どういうことかピンとこない人は、ケン月影のエチエチ時代劇漫画の導入部分を見ればわかるかも。オレもちょっと納得したわ(笑)
10月28日:オチはないけど
オレは「和服(着物)はただの衣服である」と言ってる。それに対し、衣服などと軽々しいものではない、日本の伝統文化が云々、と反論する人がいるかもしれない。
でも、オレの言葉には続きがある。
ただの衣服なんだから、日常でも非日常でももっとじゃんじゃん着ていいんだよ、実際にオレは仕事以外は和服だから。
何度か言ってるけど、和服は「聖闘士星矢の聖衣」や「ドラクエのロトの鎧」のように、最初から「伝統の衣」として存在してたわけじゃねえの。
着るもの(衣服)として、あらゆる日本人が生活のあらゆる場面で千年以上に渡って着続けてきた。だからこそ生地(反物)をはじめ様々な業種や文化が発展し、その結果として「長年にわたる日本の伝統文化」になったわけでさ。
伝統だのなんだの上っ面をなぞって「ハレの日だけ」着るよりは、大昔の人らのように着るものとして「ハレの日もケの日も」じゃんじゃん着るほうが、名実ともに伝統文化を紡いでいけると思うんだけどね。
10月20日:どれだけ着てるかだよ
「和服(着物)は孫の代でも着られる」こんな話を聞いたことある人いると思う。これ、間違いではないんだけど「生地の劣化具合による」という条件付きなのね。
収納方法というか保存状態によるのはもちろんだけど、そもそもその着物を爺さん婆さん、父さん母さんがどれだけ着てたかが重要になる。
式服礼服の類なら、そうそう着るものじゃないから持ちはいいだろうけど、爺さんがよく着てた着物なんてのになると、着用頻度が高いから、あちこち傷んだり生地が薄くなったりしてる可能性が高く、自分どころか父さんすら着られるかどうかになるわけ。
聞いた話で、婆さんだか母さんだかの長着を仕立て直してほしいと、娘さんが仕立て屋さんに持ってきたらしい。で、触ったら生地が弱ってて、直しても 着用できるかどうかわからないって伝えたけど、それでもやってほしいと言うので仕立て直したんだと。そしたら案の定、2-3回着たら生地が裂けちゃったん だってさ。
それにオレ自身、いくら元が古着とはいえ、何着か生地が裂けて着潰してるんだよ。縫い糸が切れたら縫い直すとか、部分的に当て布つけたりとか、自分で修繕しててもなおそうなるわけで。
というわけで、冒頭のことをオレが言うとしたら、
「うーんそうだねー、和服(着物)は仕立て直しができるから「モノによっては」孫の代でも着られる可能性はあるかもよ?」
10月18日:ちょっとだけ
ちょっとだけ政治の話というか。
「世襲議員はダメ!」って意見があるけど、オレは世襲か新人かは関係なくて、本人が有能かどうかってだけじゃないかなと。
だって、世襲がダメなら新人なら良いのか?って話になるし、そういう考え方って、あの事件の犯人はアニオタだった→アニオタは犯罪予備軍!とかやるテレビやマスコミと同じじゃないのかな。
ただ、世襲議員でポンコツが出てくる要因のひとつに、本人は政治家をやる気がない、あるいはただのボンクラ息子(娘)なのに、先代のしがらみというか政党や支援者から「担ぎ上げられる」のはあると思うけど。
なんにせよ、政治の世界に限らず金と権力が集まる世界って、オレら一般人の考えの及ばない別次元の世界だと思うのね。それでも、有能な人が議員になって、この日本って国を、日本人が暮らしやすい国にしていってくれたらなと。
9月10日:新ネタ更新
とりあえず適当コラムの新ネタ書き上がりました。後日、多少修正するかも。
「「着物」という言葉はいらない?」
オレが気にしすぎだとは思うけどね(笑)
8月26日:それ浴衣なの?
この前ネットで、不思議なものを見つけた。
「デニム地の浴衣」
オレが物知らずならいいんだけど、デニムって、早い話がジーパンの生地だよね?厚手だけじゃなく薄手のがあるのは知ってるけど、あの生地だよね? で、デニム地の「長着」があるのは知ってるというか、デニム生地でこしらえた長着なんだね、ふーんって話だけど、それの「浴衣」ってどゆこと?
デニムの「長着」とデニムの「浴衣」の違いってなに?どこ?(笑)これ、買った人がそう言ってるんじゃなく、そういう商品名で売られてるのね。
もう和装業界自体が、長着と浴衣の線引きがわからなくなってるんじゃねえかな。もう少し正確に言えば「着物」と浴衣かな。
......と、ここまで書いて、新ネタ思いついた。
予告(でん!)ちゃんちゃんちゃらんちゃらららん〜次回、最後のシ......じゃなくて「着物「表記」はもういらない?」この次も、サービスサービスゥ!(でも未定)
8月25日:和服のときの持ち物
まだ続きってほどじゃないけど。
和服(着物)を着てるときにどんなものを持ち歩いてるか、どんなものをカバンに入れてるか、という話。
オレがカバンに入れてるのは、たばこ、ライター、電話、財布(お金)、交通系カード、家のカギ、これだけ。
長着を着てるときだけは、手ぬぐいを懐に入れてはいるけど、使うのは汗かいたから汗を拭くか、トイレなどで手を洗って手を拭く手段がないときぐらい。先日さんざん書いたように、メシ時には一切使わないからね。
昔は、たすきがけができるように腰紐もカバンなりに入れてたけど、まあ使うことがないので持ち歩くのやめました。扇子もよく行方不明になるし、特に冬場は寒くてパタパタする必要がないので、これまたやめました。
(これ書いてて、もういい歳だし、さすがに行方不明=紛失することもないだろうから、暑い時期は扇子を持ち歩くのを再開しようかなと少し思った。)
どんなものを持ち歩くかは、洋服和服関係なく人によっていろいろあるだろうけど、それを置いとけば「和服(着物)だから」ってのは特にないかな。
オレはほんと「着る服が洋服→和服になっただけ」なんでね。
8月21日:こんなのがヒントになる?
昨日の続きだけど、少し方向性を変えて。
オレが「和服(着物)は衣服、着るものだ」ってのに気づいたのも、こんな感じの話の流れからだったわけ。
「着物で飲み食いするときには、着物を汚さないようにエプロンや手ぬぐいを活用する」これ自体は、そこまでおかしいことを言ってるわけじゃねえの。 だってせっかく着物を着てるんだから、汚したくない汚さないようにしたいってのは当然というか、ごく当たり前の発想に「思える」でしょ?
ただ、坊さんや神社に勤めてる(務めてる)ような人でもないかぎり、今のオレぐらい和服を着る人でも「仕事のときは洋服」だし、たいていの人は洋服を着る頻度のほうが高いと思うのね。
例えば仕事中の昼飯でそば屋に行ったとする。エプロンどころか手ぬぐいも使うことなく、そのままずずずーってそばを食うと思う。でも休日の昼間に着 物でそば屋に行ったら、エプロンや手ぬぐいで防御?してから、ずずずーってそばを食うと。下手すりゃ、着物を汚したくないからそば屋には行かないかもしら ん。
洋服のときにはエプロンをしないのに、着物のときにはエプロンをすると。洋服のときにはどこのメシ屋でも行けるのに、着物のときはメシ屋が限られると。洋服か着物かで、所作や作法あるいは行動パターンにズレ?が出てくるわけ。
ここでたいていの人は、最初に書いたように「だって着物を着てるんだし、汚したくないし」と、ズレが出るのは当然だと流してしまうんだろうけど、そのズレに対して少々めんどくささを感じてる人とかだと、ふと考えてしまうかもしれない。
「洋服だったらなにも気にすることないのに、着物のときはメシ食うときも気を使わなきゃいけないからめんどくせえな、
どっちも同じ「着るもの」なのによ......」
「和服(着物)は衣服、着るものである」ってのは、難しくもなんともない、ごくごく単純な考え方というか発想なんだよ。でもそこに「自分で」気づけるかどうかは、着物を着ることに息苦しさ?を感じるかどうかなのかもね。
8月20日:つまんねえ話だけど。
どんな和服(着物)をどんなふうに着ようが、普段着日常着の範囲であれば、それは着る人の自由、服装の自由です。これは大前提。
大前提なんだけど......うーんって思うことはある。
特に着物を着ているとき、飲み食いするのにエプロン使ったり、手ぬぐいをエプロン代わりにしたり膝上に置いたり、果てはたすきがけしたり。「着物が普段着なんで、食事をするときはいつもこうしてます」
それホントに普段着か?
オレは今まで、飲み食いするときに和服でエプロンをしたのは2、3回ぐらい。ただしそれは、すべての席にエプロンが備え付けてあった、いわゆる屋外 BBQの店舗でのこと。それ以外は、店側から申し出があっても断ってるし、それでも心配なようなら「なにがあっても絶対に文句言わないから大丈夫」的なこ とを言ってる。
膝上に手ぬぐいを置くのは、着物を着るようになった最初のうちはやってたかな。汚したくないからっていうより、そうするのが着物のマナーというか作法だと勘違いしてたから。そのうち気づいて、これやる意味ねえわとやめました。
「大前提」があるから、エプロンしようがどうしようが着る人が判断して自由にすりゃいいよ。
でもさ「着物を着てるとき限定で」ちょっとした高級店とかならともかく、そこらのうどんそば屋やラーメン屋とかで、汁はねが気になるからとエプロンして食うってどうなん?まわりの(洋服の)客は誰もしてないのに、自分(ら)だけエプロンして焼き肉してるってどうなん?
飲み食いするときにエプロンする普段着ねえ、ほーん。
普段着とかカジュアルとかよく聞くけど、それって正式なフォーマルではないってだけの、実際は準フォーマル的な感覚で着てんじゃねえのかなと。ガチで和服(着物)を普段着にしてるオレからしたら、そこがモヤモヤするんだよね。
ただまあ、そんなのにいちいち反応してるオレも、器がちっせえというか、自分でいやになるというか。隣の芝生は見ないのが一番ですな(笑
5月1日:画像更新
サイトの「着物:準備〜羽織」の画像を大きく&イラスト化しました。
サイトで使ってる画像の元画像の大半は、前のPCが壊れたときになくなっちゃったので、実写?画像を大きくしようとしたら全部撮り直さなきゃいけないけど、着方とかはイラストでやれるならそのほうがいいかなと。
昔、WEBマガジンかなにかの編集?の方から、ウチの帯の結び方の画像を使いたいって連絡があって、ウチの画像を元にイラスト化して掲載してくれたんだけど、その完成原稿?を見て「見やすいし、絵心ある人いいなあ」って思ってたのね。
で、以前「柄物の組み合わせ方」の画像を差し替えたでしょ。あのイラストは、オレが着物を着てる写真を「トレース」して多少修正したやつなんだけど、ああ、この方法でやればサイトの小さい画像でもやれるんじゃね?とふと思いついてやってみたわけ。
まあガチのきれいなイラストはさすがにオレじゃ無理だけど、解説画像なら簡略化したイラストでもいいでしょ(汗
4月26日:お湯のみ浸けおき洗い
絶賛春真っ盛り、というわけで、冬物を洗濯して片付けた。それで今回試したのが、洗剤は使わずお湯(約40度)だけで浸けおき洗いをしてみる、ってやつ。
・洗うやつを事前にチェックして、例えば醤油のシミなどといったマジの汚れ?があるなら、当然そこはピンポイントで(洗剤を垂らして)ゴシゴシはする。特にないようであれば洗濯たらいへ直行。
・襦袢も長着も首回りが汚れやすいけど、襦袢には半衿がついてるし、長着にはオレは当て布をしてるのが多いので、それらは次のシーズンに交換すると いうことで特には気にしない。袖口は、冬場はたいてい長袖肌着を着ていて地肌に接することがないので、首回りのように汗や皮脂汚れはないと判断。
・お湯を張った洗濯たらいにドボン、2-3分ほど押し洗いをして、そのあと10-15分ほど放置。すすぎはせず洗濯機で脱水→干す。
結局「お出かけ用」のやつなので、醤油のシミとかはできる可能性はあるけど、あとはホコリとか、せいぜいついても泥ハネとかその程度なので、別に洗剤使って洗濯機ブンブンするほど汚れてねえだろと。
皮脂汚れの類も、長袖肌着や当て布をするオレの場合は、冬物はそこまで心配するほどでもないだろうと。そもそも冬場は寒いから汗かくほどじゃないしね。
それにそもそも、適度に洗濯してるのと、なんせオレが着るだけだし(笑)そのかわり、洗剤を使わないぶん、洗濯の頻度は増やすつもり。
冬物は片付けちゃったので、実践本番は次のシーズンからになるけど、うまくいけばいいかなあと。
ああ、夏物はやっぱ汗かくから、今までどおりジャンジャン洗濯するよ。それでも、洗剤は使わずともなるべく早くお湯(夏は水温上がるから水でもいいか?)につけてやれば、汗や皮脂汚れはけっこう飛ばせるだろうから、それだけでも効果はあるかなと。
ちなみに一番のメリットは、洗剤を使わないからすすぎをしなくていいので、水の節約どうこうより単純に楽ですはい。特に冬物は厚手のものが多くて、ほんとすすぎめんどくせえから。
3月6日:トップページ変更
見ればわかるけど、サイトのトップページの構成を変えました。
以前はPCで見るのを前提に、あまり縦長にならないよう、各ページへのリンクをずらずらっと並べてたんだけど、今はスマホが普及してるので、多少縦長でもリンクをタップしやすいように?並べ替えました。
そのため、PCで見ると右のほうに空白が目立つようになったけどね(笑)文字をセンター寄せすりゃいいんだけど、通常のページは画像以外は全部左寄せになってるので、それに合わせるってことで。
あと、書き直してる途中で止まってる(放置ともいう)ページは、ひとまずページへのリンクを外しました。「作務衣と甚平」は、着方解説のところから各種和服の解説のところへ移動させました。
令和7年1月5日:謹賀新年
遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。

去年末から年始にかけて、風邪ひいたというか体調不良でして。まあなんとか休み明けまでには回復しました。
今年もたまにぐらいしか更新はしそうにないですが、本年もよろしくお願いします。
10月8日:久しぶり新ネタ
「おまけネタ」に「帯の位置は人それぞれ」って新規のページ追加しました。文章はあとで多少加筆修正するかも。
9月15日:また更新
帯の締め方結び方「帯を締める位置の目安」の画像を差し替えました。
全身像を追加したので、全体のバランス?で見て、帯がどの辺りに来るかがわかりやすくなったかと。
9月11日:更新
久しぶりにサイトのほう更新。
着方の参考例「柄物の組み合わせ方」にあった画像を差し替えました。画像を差し替えただけで、内容自体は変わってません。
以前は、オレが適当に描いた4頭身ぐらいのヘタクソなイラストだったけど、5頭身ぐらいのイラストに変更して、少し大きくした。

新しいイラストもオレが描いたやつだけど、自分が着物を着てる写真をいわゆるトレース&調整したやつなので、少しはそれっぽい絵になってるかと。
(C) 2007,2019 バカガエル.