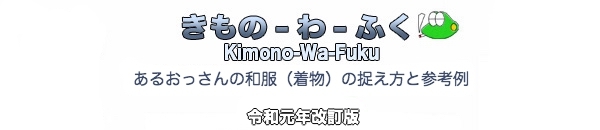「着物」という言葉はなくてもいい?
和服(着物)について解説してるサイトが「着物って言葉はもういらない」とか、頭おかしくなったんじゃないのか?!と思うかもだけど、読んでもらえ れば、そこまで無茶なことは言ってないはず。
元に戻したいのよ、オレは。
和服、着物、長着の区分
このサイトのトップにある「初訪問の方へ」で説明してるように、このサイト(=オレ)は解説上「和服、着物、長着」を意図的に使い分けてる。そのま ま引用すると、
>和服:洋服と区別するための総称。作務衣や甚平、衣装や装束なども含む。
>着物:一般的に和服あるいは着物姿と呼ばれる恰好や着方。袴も含む。
>長着:一般的に着物と呼ばれる、着るモノ(アイテム)の正式名称。
これに加えて浴衣に関しては「浴衣と着物(長着)の違い」で解説してあるように「現在市販されている浴衣=長着」としている。これらを簡単にまとめ ると、
広い範囲:和服>>着物>>長着=浴衣:狭い範囲
ということになるかな。これを念頭に置いた上で、以下の話をどうぞ。
「着物」がなくても話は通じる?
「これは大島紬で仕立てた着物です」
ごく普通の文章だけど、これを別の言い方ができるのかと考えてみておくれ。ちなみに生地の固有名に特に意味はないよ。オレだったら、
「これは大島紬で仕立てた長着(と羽織)です」
着物→長着(と羽織)に置き換えただけなんだけど、よーく見比べてほしい。
最初の文章だと、大島紬で着物を仕立てのはわかるけど、着物の「なに」を、羽織なのか長着なのか、はたまた角袖やコートなのか襦袢(まあこれはない か)なのか、そこまではわからない。
でも置き換えた文章だと、着物という言葉を使ってないのに、着物の「なに」を仕立てたかまでわかるでしょ。
今は「長着」って呼び名があまり一般的ではないので、知らない人とは「長着ってなに?」となるだろうけど、知っている(知っ た)人となら「着物」よりもっと正確に意思疎通ができるってこと。
となると......「着物」という単語は、使わなくても問題ないと思いませんか?
実はここ1年(この文章は令和7年8月に書いてます)ぐらい前から、このサイトの文章以外では会話とかでも「着物」を使わないようにしてる。相手が 「着物」と言っても オレは「和服」「服」「長着」で返してるけど、問題なく意思疎通はできるみたい。
「和」服と「洋」服
実はこれ、単語が「着物」ではなく「和服」であっても同じこと。
「これは大島紬で仕立てた和服です」
「これは大島紬で仕立てた長着(と羽織)です」
「和服」のほうが、作務衣や装束なども含まれるぶん範囲が広いので、長着(と羽織)に置き換えたほうがよりわかりやすいのは間違いない(笑)
だったら「着物」だけじゃなく「和服」も使わなくていいじゃん、と思うかもだけど「和服」には別の使い道がある。それが「和服と洋服」ってやつ。
和服と洋服以外にも、いろんなもので「和(日本)と洋(欧米)」を対比した言葉があるでしょ。例えば和食と洋食とか、よく使いそうなのが和風と洋風 かな。
現代人が洋服をただ「服」と呼んでるように「和服」もあえて使う必要はないんだけど、それこそこのサイトのように文章などで説明するときに「和と 洋」の区別として意味を伝えやすいってわけ。
実際、このサイトの文章から「着物」をなくそうと思えばできるよ。ただ、世間一般の認識として「和服=着物」であり、上で書いたように「長着」が あまり一般的ではないので、今でも「着物」を使ってるわけ。
昔は和洋関係なく全て「着物」だった?
実際はどうだか知らないけど、そもそも「和服」という言葉は明治時代以降に生まれたとオレは思う。あるいはもっと近代になってから、歴史 の研究?とかで服装を大まかに分類する際に、便宜上?そう呼ぶようになったのかもしれない。
というのも、江戸時代以前は「洋服」というモノがほとんど存在しなかったので、その言葉自体もなかったんじゃないかなと。あったのは「呉服」ぐらい かな。
じゃあ服装のことをなんと呼んでたかというと、現代人がすべて「服」と呼ぶように、昔はすべて「着る物→着物」だったんじゃないの かなと。
例えば、今は固有名で区別して呼ぶことが多いけど、靴も雪駄も「履き物」だし、お茶もコーヒーもジュースも「飲み物」だし、他にも食べ物乗り物入れ 物置き物など「こうする(動詞)+モノ(物)」という総称はいろいろあるでしょ。
時代とともに新しい言葉ができたり、言葉の意味が微妙に変わるのはよくある話だけど、「着物」の場合は「る」が省略されてしまって、現代においては それが固有名に変わってしまったというか、都合よく利用されてる?というか。
未来から来たネコ型ロボットでもいたら、歴史の資料や専門家の意見じゃなく、当時の「生の声」ってのを聞いてみたいもんだよ(笑)
昔の「着物」に戻したいだけ。
別にさ、言葉狩りをしたいわけじゃねえの。意味が通じるなら、和服だろうが着物だろうが長着だろうが、使いたい言葉を使えばいいんですよ。
でも相変わらず「着物は別格」のような雰囲気が、界隈?にはあるというか。だったら、オレは別格扱いするのもされるのもイヤだから「着物」って言葉 は使ってやんねえよ、ってのが今回のネタの発端。
オレは和服(着物)を、昔の「着物」に戻したいだけ。
日本で1000年以上続いてきた、伝統的な服飾文化の「本質」を守りたいだけ。
着る人にとっても着ない人にとっても、昔のように「着る物」になったほうが、日常で当たり前の「服」になったほうが、なにかと都合がいいと思うんだ よ。
なのに、特に着る人側が「着物は別格」なんて考え方をしてたら、広がるものも広がらなくなってしまうんじゃないかなと。それとも、そんな自分(ら)を別格扱いしてほしい、自分らは別格だって言いたいのかな?(笑)
もし今の「着物」が違う路線に行くのであれば、オレは「着物」から離脱するかもね。オレが着てるのは「和服」であって「着物」ではない、と。そ うなってほしくはないけど......まあなるようになるさ(笑)
浴衣→ゆかた、着物→きもの
ついでだから言っておこうか。
ここのサイト名も「きものーわーふく」だから、あまり偉そうなことはいえないんだけど、最近?よくみかける、漢字表記ではなくひらがな表記で「きも の」「ゆかた」とかやってるの、あれもなんかもやもやする。
ひらがな表記にすると字面が和らぐ?ってのはわかる。口から言葉として発せれば、漢字ひらがなカタカナ関係ないのもわかる。
でも「浴衣」だと「浴」の漢字があって、浴→入浴→風呂を連想させる(ただし本来の浴衣はこれが正解)ので、それを誤魔化すために「ゆかた」としだ したんじゃないかと。
「着物」も着物→着る物となってしまうので、上で書いたような別格感を出すために「きもの」としだしたんじゃないかと。
まあこれはオレの感じ方の問題であって、そこに他意はないと思いたいんだけど、もしそうじゃないなら……本質を見失ってしまうと思うぜ?
ちなみに、時代劇の看板とかでは「きもの」になってるのは、識字率とか当時の教育水準の関係だと思うよ。そもそも「着」「物」って漢字がいつ頃から 一般的に使われるようになったかってのもあるだろうし。
(C) 2007,2019 バカガエル.